
もやむのサイト
登場人物紹介
(全て読むの面倒&全てを把握されてない方のための補足。
アイコンイラストは本編には一切関係ありません)
【璃王】

魔導学院の生徒。夢見科所属。いつも何かとからかってくるステイリーの友人。
ステイリーと研究室での話し合いの後、医務室で一人休んでいた。
移動魔法科のラミィのことが好き。
【ルリア】

魔導学院の生徒。ラウンジで告白するも振られてしまうが後に書庫にてその理由を知らされる。
そ�の後、魔力を使いすぎたステイリーをつれて医務室へとやってくる。
優しく純粋で天然な女の子。
【ステイリー】

魔導学院の生徒。病に倒れた友人に対し自責の念を抱えている。
今まで誰にも話しては来なかったが、告白を機に璃王とルリアには話をした。
ルリアのことを好きだと自覚はしているが今まで通りの友だち関係を望む。
*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*
『ラウンジ退出後-医務室-』
【璃王】
「――――――、…」
眠りから覚醒する意識。
見慣れぬ天井、いつもと違うベッドの感触に違和感を覚えていると、先ほどまでの夢見の研究室での会話が蘇ってきた。
反芻する。
研究室から食堂に行ってその後半ば強制的に―――――、そうだ、ステイリーに医務室に連れてこられたのだった。
横になったまま軽く体を動かしてみる。
大丈夫、辛さはない、回復したと思って差支えなさそうだ。
保険医は用事があると言って、治療後に出て行った。
つまりこの医務室には自分以外誰もいない、はずだ。
起き上がるのも面倒で寝返りをうつ、そして隣のベッドに先ほど別れたばかりの件の友人の姿を見つけた。
「ステイリー…?」
眠っているようである、何があったと思わず起き上がった矢先に人の気配。
上体ごと振り向けば、窓辺に小さな星が光るピンクの髪が印象的な少女が立っていた。
見ればその顔は今にも泣きだしそうだ。
「――――ルリア?」
【ルリア】
医務室についてステイリーを寝かしつけ、改めてやり取りを思い出して思わず赤面した。
けれども
『だから僕はもうこれ以上…幸せになるつもりはないんです』
その言葉が頭を反芻する
考え込んで落ち込んでいたら声がかかった
「え…?あ、璃王さん…。おはようございます」
そういえば彼は具合を崩していたのを思い出す
「失礼しますね」
医者を目指す性分で額に触れて熱を確認すると通常の体温
顔色も良くなったのに安心する
「よかった。具合良くなったみたいですね。喉はどうです?」
【璃王】
「大丈夫、有難う」
短く答えて。
表情と態度のちぐはぐさに思わずため息が続いてしまう。
「……… …
ルリア、君さ、ボクの世話なんてやいている場合?」
ベッドに上体を起こし、寝ているステイリーと目の前に立つルリアの顔を順に見やる。
「ステイリーと、何かあったんじゃないの?」
確信を込めて問う。
【ルリア】
「え…!?あ…あの…その……それは……」
いきなり確信を持った事を言われ慌てる
良い淀むのはルリアの癖だ。親しい訳でない人とは患者相手以外は上手く話せない
璃王とはステイリーを通して何度かと、書庫で本を何度か選んだ事のある程度の”知人”
ステイリーの友達で優しそうだから知人の中では比較的話し掛けやすい。それだけの関係だ
「それは…えと……」
そういえばエリザがステイリーは璃王に任せたと言ってたのを思い出す
つまり二人は何かを話したのだろう
しかし何を話したか分からない以上さっきのやりとりをどこまで話して良いのか分からない
「………喧嘩は…してません…。えと…”友達”…ですから大丈夫です。
ステイリーさんは…少々魔力を使いすぎて……。それで寝てるだけです。はい」
人に教えて差し障りのない結論を伝えた
【璃王】
「”友達”、ね」
先ほどまでのステイリーのやり取りを思い出す。
そしてその前にラウンジであのような別れ方をした二人が今ここで一緒にいる、何かあったと思うのが当然だ。
(それも泣きそうな顔で”友達”と言われてもね)
ひっかかる。
ならば友人の為に動くべきか。動くならどう動くか。それとも二人に任せるべきなのか。
思考を巡らせているその時、カサリと、無意識に胸に当てた手がポケットに入れていた何かを探り当てる。
――今度相談させて下さい―――
そう綴られていたメモ。
「―――そういえば、ルリア、君、ボクに相談があるって言っていなかったっけ」
まずは手近な所から、と切り出してみる。
【ルリア】
そういえばそうだった。バタバタしていてすっかり忘れていた
あの時はとにかく勇気が欲しくて自信を身につける方法を聞きたかったのを思い出す
ポケットに入れたままのお守りの鏡に指を当てた
勇気の出し方は友達に教えて貰えた
「その……それは…もう大丈夫になりました…。
………済みません。気にさせて……。有難うございます」
これで話を終わらせれば良い
それなのに、納まらない気持ちは口を勝手に滑らせる
「……ですけど…今も聞いて貰いたい話はあるかも…しれないです
でも…それは……ステイリーさんの事情が絡むから……あまり言えなくて……」
自分で言って吃驚した。
それにしても何で自分は話すのがこんなに下手なのだろうか
これでは折角向こうが気にかけてくれたのに気を悪くしてしまうかもしれない
恐る恐る璃王を見てみた
【璃王】
――ステイリーの事情が絡む…
直感、先ほどの話をルリアにしたのだろう。
(さっきの今で話したのか。一歩踏み出したことは認めるけどさ)
けど、結果相手にこんな顔をさせていいのか、と――顔をあげると恐る恐る向けられた視線に気付いた。
その視線は物問いたげに見える。
「ルリアも聞いたんだね。ステイリーの友人の話」
事情は知っているから、と頷く。
そしてやんわりと笑みを浮かべて言葉を紡いだ。
「話、ボクで良かったら聞くよ」
【ルリア】
「……お友達が…入院した経緯と……ステイリーさんが…その…思っている事も……?」
念のために確認すると璃王はしっかり頷いた
ただの知人に言う事じゃないのは分かってる
でも、今の悩みはステイリーの事を知る人にしか話せない
つまり目の前の人にだけ
悩んだけど相手の好意に甘える事にした。
立ったまま話すのは相手に悪いので丸椅子を引き寄せ璃王の足元の横に座り目線を合わせる
ステイリーがまだ寝てるのを横目で確認して口を開いた
「話は友達の事でなく私の事です…。
……私は…本当にステイリーさんの傍に居続けて良いのかと……」
璃王は訝しむ顔をしたが続けるよう促した
頷いて続ける事にする
「…私…知ってると思うのですが…ステイリーさんが好き…なんです。……さっきステイリーさんにも自分も好きだって告白されました…
でも、付き合えないって…。これ以上幸せになれないからって…」
自分はもうバレバレだろうしそこまで話した友人相手なんだから、きっと彼の気持ちも知ってるだろう
そう思い互いの気持ちを告げた
「…好きな人と居るのは幸せな事ですよね…。
私は…望んでしまったんです
自分を責めてる人に、私の望みで傍に居たいと…」
あの時は星が綺麗で
抱きしめられた腕が温かくて
我が儘でも離れなくなかった。けれど
「でも……幸せを望まない程責任感が強い…そう言う人に……私が傍に居たら……重くなるのでは……って…
傍を望むのは…間違っていたんじゃ…って……」
ルリアはステイリーの言葉に自分の父親を思い出ていした
父は母を治せなかった
その後悔を、痛みを未だに引きずっている
せめて支えたくて仕事を手伝い傍に居続けた。けど父親は苦笑いばかりで距離は埋まらなかった
ある日父が珍しく酔っていた時言われた言葉
『日に日に母に似ていく君を見るのが辛い。嫌でも思い出す』
傍に居たい
そんな気持ちでやっていた行動は、逆に相手の罪悪感を増幅させて居ただけに過ぎなかった
わざわざ国まで出てこの学園に来た理由の一つにこの事もあった
重なる
自分は好きだから傍に居たい
けどそれは相手の罪悪感を重くする行為に等しいのではないのか?
そう考えずにはいられない。傍に居たいと言う気持ちに段々罪悪感が募ってきた
【璃王】
「あの、バカ」
気持ちを伝えてその上突き放すとか、バカとしか言いようがない。
「あいつが何故、その話を君にしたんだと思う?」
本当に望んでいないなら、そんな話をしたりなどしない。
最初から突き放しておせばいい。
そう出来ないほどに、ルリアの存在が大きなものになっているのだ、と。
きっと、その友人と同じ位、ひょっとしたらそれ以上に。
そう告げそうになる言葉を抑えた。
(互いにそんなことにも気付かないとはね)
「本当にステイリーのことを想うなら、傍に居て支えてあげればいい。
それとも、見返りを期待できない愛情を注ぐのは辛い?」
続く言葉は挑発するような響きを帯びていた。
【ルリア】
何でそんな話を?それは考えてなかった
でも考えても答えは出ない
「…分かりません…分からないんです…私…」
本当に相手を思う
それは簡単な事でない。人付き合いが下手な自分は失敗を繰り返していてばかりで自信が持てない
「…ただ…傍に居たい…居て欲しい……
私だってステイリーさんに与えて貰った分、それ以上を与えたいんです…!見返りなんて…なくてもそれ以上をもう貰ってます!」
涙が溢れる
こんなにもこの気持ちは大きくて、強い
「恋人になれなくたって…構わないんです…!
ただ…怖いんです…!私の気持ちがステイリーさんの罪悪感を刺激するんじゃって…!
相手を押し潰してしまうんじゃないかって…!
私はステイリーさんを傷つけるのが何より怖いんです…!!!」
一気に言い切って肩で息をする
人にこんなに大声出したのは初めてかもしれない。
【璃王】
想いの丈が込められたルリアの声が医務室に響く。
チラと横目でステイリーを見るも、目を覚ました様子はない。
ルリアの気持ちは明確だ。
傍にいたい、けれど負担になるかもしれないという迷いの間で葛藤している。泣くほどに。
ならば、その迷いを取り除いてしまえばいい。
ベッドから降り、ルリアの横に立つ。
何事かとこちらを見たルリアに問いかけた。
「若し、互いに想いを抱えたまま傍を離れるという選択をしたらどうなるか、想像がつく?君がこのままステイリーのそばを離れたら――」
そして答えを待たず、眉間に手をかざす。ごめん、と、小さく呟いて。
――眠りの魔法、意識を失った身体がぐらりと後ろへ倒れこみそうになるのを抱き留めて、ベッドへと横たえた。
先ほど激高した際に溢れた涙が枕を濡らした。
「これは夢、けれど遠くない未来起こり得る可能性も秘めているifの夢」
そう呟くと、眠る少女に夢見の魔法をかけた。
ステイリーの未来の一つのヴィジョンの夢を。

【ステイリー(if)】
――――…講義を受けるため廊下を歩く。すれ違う友人知人に軽く挨拶を交わすいつもとなんら変わらない日常。
只一つ変わったのは、よく通っていた書庫に足を運ばなくなったことだ。
書庫の前を通りかかりふと足を止めるが、苦い顔をして足早に立ち去る。
…彼女は離れていった。
僕の負担になりたくないから、僕を傷つけたくないから、と。
彼女が望まない以上、僕はそれを止めることは出来なかった。
それ以来、見かけることはあっても、言葉を交わすことすらなくなってしまった。
もうあの星飾りの魔法もとっくに解けているだろう。
後に残ったのは、どうしようもないほどの虚無感。
広い講堂に響く先生の声。眠たくなるようなうららかな日差しの中、文字を書く乾いた音と共に鳥の楽しそうな囀りが聴こえる。
そして一秒ずつ当然のように進む秒針。
僕がルスから奪ってしまったなんてことのない日常。なんてことのない、普通の幸せ。そして未来。
時たま過ぎるそんな考えが急に罪悪感へと変わり押し寄せる。
…どうして僕ではなくルスだったんだろう
あいつは空の下が一番似合うのに
…どうして僕はルスを救えないんだろう
ルリアさんまで傷つけてしまったというのに
どうやって今まで耐えてきたのかわからない
あぁ、もう
自分が無力すぎて…嫌になる
…どうして僕は……ここにいるんだろう…――――
【ルリア】
手を思わず伸ばした
けど届かない
ここは夢の世界だと気付く。だからなのか伝わってくる、聞こえる
自分が離れた後のステイリーの気持ちが
それは痛い位の虚無感、それに孤独
待って…!違う…!!そんな事望んでいない…!!ただ、ただ…傷付けたくないだけ…!!そんな…気持ちになって欲しくなんてない……!!
どんなに叫んでも届かない
伝わらない
だってこの世界の自分は傍に居ないから
……あぁ……そうか…
傍を選ばない事だって相手を傷付ける行為なんだ
何で気付かなかったんだろう…?
人が傍にいる幸せを教えて貰っといて……何自分は相手に恩を仇で返す真似をしようとしてるのか!!
同じ傷付けるなら、せめて一人にしたくない…!!傍で支えたい…!
そこで目が覚めた
涙が溢れて止まらない
何より先にステイリーに駆け寄った
そうだ。この人はちゃんと言ってくれた。”傍に居て下さい”って……
この人は、傍を望む言葉を言ってくれたじゃないか…!!!!
「…璃…王……さ………。私……私……ゴメン……なさっ……!!」
起こさないように布団の端にしがみついて、ただ、泣いた
【璃王】
横たわるステイリーと傍で泣きじゃくるルリア、二人を見つめ静かに息をついた。
(お役御免、かな)
ルリアの表情に、先ほどまでの迷いは見られない。
気持ちが定まった今、後はステイリー次第だ。
知らず口元に笑みが浮かんだ。
「はい、これ」
一向に目を覚まさない友人の代わりに、ポケットから取り出したハンカチを手渡す。
「落ち着いた?」
そして一旦言葉を区切って、謝罪の言葉を口にする。
「さっきのこと、勝手に魔法をかけたこと、謝るよ、ごめん」
【ルリア】
やっぱり今のは璃王の魔法だったのか、と納得した
「いえ……。むしろ…有難う…ございました…」
こうでもされなければ、相手の気持ちなんて考えもしなかったと思う。だから悲しい夢だったけど決して謝罪される行為ではない
ハンカチを手にしながら借りるのは今日で二枚目だなって考える
ステイリーを起こさないよう起き上がり、璃王に目配せして後ろに下がり、間にカーテンを引いて何となくそのままさっきまで寝ていたベッドに二人で座る
息を吐くとずっと自分の中でわだかまっていた罪悪感が一気に軽くなった
確かに自分は父親に苦しい気持ちを与えた。でもそれ以上に傍に居ることに意味はきっとあった
だって一人の寂しさは何より辛いから
だからこそ、今度は自分が傍を望んでくれたステイリーの隣に居続けよう
いつか後悔しない為にも
大好きなこの気持ちに素直で居よう
心は固まった
……そして今頃気付いた
自分はさっきまで今座ってる場所の逆にある丸椅子に座っていた筈…だ
……さっきは間違いなくこのベッドで寝てた。つまり………
「……重くて申し訳ありませんでした………」
…顔から火が今ならふける気がしてならない
【璃王】
一瞬で真っ赤になったルリアと予想外の反応に思わず笑いを漏らしてしまう。
何とも女の子らしい反応。
「大丈夫、ボクこれでも男だから」
しれっと。答えになっていない答えを返した。
そして目の前の少女のくるくる変わる表情を見つめながら聞こえるか聞こえないか小さく呟く。
「…頼んだよ、ステイリーの事」
けれど、次の瞬間には悪戯を思いついた子どものような表情を浮かべる。
「そうだ、何なら今度は幸せな夢でも見せてあげようか」
にこにこと。
悪戯っぽく笑って、先ほどのように手を伸ばそうとした。
【ルリア】
笑われた上に否定されてない気がしてならない…
あれだ、お菓子作るのに味見し過ぎたんだ…!!…気をつけないと!!
そんな葛藤をしていたせいで小さく呟かれた言葉は届かなかった。
とりあえずのびてくる手を手で軽く押し返す
男の人の手に僅かに緊張する
「え、えと夢はダメじゃないですがその前に…」
彼は知らない
隠して抱えていた父親への罪悪感ごと軽くしてくれた事を
「改めて、有難うございました…!本当に…!
あと…大声出してゴメンなさい…」
誰かに何かをして貰えるのは奇跡みたいな事なのかもしれない
例えそれがささやかな物だとしても
そこで気が付いた
璃王にとって自分はただの友人の友人。自分に対してここまでしてくれる理由は一つもない
つまり、璃王はステイリーの為にこんな事をしてくれたのだ
…やっぱりステイリーは素敵な人だな、と感じる
彼の人徳故に優しい友人に恵まれている。自分もその一人になれているだろうか?
「璃王さんってステイリーさんの事好きですよね」
彼は珍しくきょとんとした顔をした
「私も大好きです。なのでお仲間ですね!私達ステイリーさん好き好き同盟です!」
失恋してからやっと、嬉しくて心から笑うことが出来た
【璃王】
「―――――――、……………」
―――――今、ルリアは何と言った?
発言までの経緯を頭の中で反芻する。
慌てた様子を見せたと思ったら悪戯に伸ばした手を押し返されて、有難うとごめんなさいを同時に言われて…そして?
なかま?いや――
「す、きすき、どう、めい… …?」
思考が固まった。
本日2度目の不覚。
【ルリア】
「そうですよ。だってステイリーさんの為にここまでしてくれたのでしょう?」
璃王もまた、友人思いで優しい人なんだ
そうルリアは感じた
(多分彼女の)ラミィは幸せ者なのだろう、きっと
相手に対して親しみが一気に沸いて来た。感情のまま言葉を紡ぐ
「私ね、璃王さんの事好きです
同じ人好き同士のお仲間ですしね!」
恋をするのはステイリーにだけ。多分これから先もずっと
璃王には恋心を知られているから変な意味には決して取られない確信がある。そもそも相手には恋人(多分)もいるし
これは親愛だ
感謝と親愛をこめて何故か固まってる彼に改めて笑って手を差し出す
「も…もし良ければ私ともお友達になって下さい…!」
そして次は、自分が相手の力になりたい。そう強く願う
【璃王】
またも固まった。
「好き、って、君ね」
何を言い出すかと思ったら”友達”になりたいのだという。
不意に笑いがこみ上げてきた。
「はは…、っはは、そう、だね。いいんじゃない、好き好き同盟も友達も」
想定外の事を言われペースを崩されてばかりだけれど、嫌な気持ちではない。
(ほんっと、無自覚の天然娘こそ最強かもしれない)
差し出された手を軽く握り返した。笑みを浮かべて。
「こちらこそ、宜しく」
【ルリア】
さっきみたいな意地悪な感じじゃない
今までとはちょっと違う。ちゃんと笑って貰えた
それがたまらなく嬉しい
その気持ちは胸に星を灯す
「はい…!宜しくお願いします」
軽く握手をして手を離す
自分もこの胸の星を彼等に与えたい。その気持ちが急速に湧いてくる
「あの、何かして欲しい事ありませんか?私、ステイリーさんにも璃王さんにもお世話になった分を返したいんです!」
と、力一杯申し出てみた
【璃王】
危うく3度目の硬直をしそうになった。
この娘は突然何を言い出すのだろう。
「……………だから、ルリア、君ね――」
無邪気すぎる物言いにステイリーの苦労が思いやられる、とそこまで考えて、思い出す。
カーテンの向こうのベッドに寝ている友人の事を。
(いい加減目を覚ましたらどうだ?)
……
寝ている友人と、無邪気な天然少女。
うん、と見る人が見れば何かを企んでいると判る笑みを浮かべた。
警戒心を抱かせないように何気ない風を装って、さらりと言う。
「じゃあ、キス、してもらっていい?」
【ルリア】
今度はルリアが硬直する番だった
今何て言われたのか頭で反芻する
…………キス…って言われた……確かに
一気に顔に熱が集まった
「…な…な……何言ってるんですか!!ラミィさんが泣きますよ!?
恋人いるのにダメじゃないですか!!!」
はっきりと恋人と聞いた訳じゃない
けどラミィとは良い雰囲気の相手の筈だ。前にひざ枕されてたの見たし多分間違いない
…そこで思い出した。自分も親しくない時期にステイリーに膝枕をしたと…。では恋人は勘違いなのだろうか?
いや、だからっといって許す訳にいかない
「…そういうのは恋人とやる事だと思います…!」
抗議をこめて軽く睨む
【璃王】
ラミィが泣く、と。想定外の台詞に思わず動揺する。
(大丈夫、ラミィも友人も裏切るようなことはしない)
頭を振って気持ちを切り替えると、ルリアの抗議の視線をやんわりと受けとめた。
「そうか、友達だって言ってくれたのに。
親愛のキスもだめなんだ」
笑みを落胆した表情に変えて、大きくため息をついた。
ステイリーが聞いていたら、わざとらしいと言ったかもしれない。
頬をとんと指す。
「ここでは、キスは挨拶代わりなんだよ。
親しい友人間で親しみを込めてキスするの、見たことない?」
視線を落として、ルリアの反応を伺う。
そしてカーテンの向こうも気配も。
【ルリア】
…頭に衝撃音が鳴り響いた…!
知らなかった……!そんなの見た事もなかった…!けど人間関係が薄い自分なら仕方のない事だろう…!!!そんな風習があったなんて…!
あそこまでがっかりして言うならそうなんだ…!
何て事だ…!!自分から友達になりたいって言っておいて無知故に怒るなんて…!!失礼にも程があるじゃないか…!!
「すみません…!まさかそんな挨拶があったとは露知らず…!!」
素直に頭を下げる
友達に親愛を伝える行為にキスが普通だったなんて…!!
何一人で勝手に意識してたんだろうか…!恥ずかしい…!!
ここでは常識!だったら大丈夫…!出来る!! そう自己暗示をかける
「…で、では…!お望みとあれば失礼します…!!!」
これは親愛。友情。
変に意識する方がおかしい!!!
そう考えルリアは璃王に近付く
カーテンの向こうの存在は頭からすっぽり抜けていた
【ステイリー】
「………ん」
騒がしくて眼が覚めた。
寝覚めの悪い頭で今の状況を思い出す。
確か…そうか、魔力を使いすぎて医務室に来たんだっけ
まだ体は重いが幾分か楽になったようだ。
ゆっくりとベッドから上体を起こす。
まどろみの中、璃王とルリアの声が聞こえた気がする。
好きとかキスとか断片的な会話が頭の中を反響していた。
夢…?
ふと横に眼をやると間切られたカーテンに2つの影が映し出されている。
確か隣は先刻、無理やり連れてきた璃王が寝ていたはずだ。
同時に聞こえてくるなにやら緊張気味のルリアの声。
何か嫌な予感がしてカーテンに手を伸ばし無遠慮に引っ張る。
…開けた目の前の光景に言葉も出ず、しばらく固まった。
【璃王】
後少しで頬に触れる、という所で肩に手を置きそっと押しとどめた。
小さく首を振る。
ルリアは何故止められたか判らない、という様子できょとんとしている。
その時。
こちらと向こうを仕切るカーテンが音を立ててひかれた。
開いたカーテンの向こうには。
動きを止め、彫刻のように固まったステイリーの姿。
してやったりとばかりに笑う。
そして固まったままの友人に何気ない風を装って声をかけた。
「やあ、ステイリー、おはよう。目覚めの気分はどう?」
憎らしくなるほどの極上の笑みを添えて。
【ステイリー】
こちらに向けられた見慣れた笑み―何かを仕向けて成功したといわんばかりのそんな笑みに思わず頭を抱え、ため息が漏れる。
だけど寝起きということも手伝い、頭がいつも以上に働かない。
「あー……、これはいったいどういう状況なのか説明をしてもらってもいいかな…?」
笑みを作りながらも少し怒気を孕んだ声で問いかける。
目覚めの気分?そんなもの、最悪に決まっていた。
【璃王】
「どういう状況も何も、見た通りだけど?」
不機嫌そうなステイリーをものともせず、対照的ににこやかに答えた。
「ルリアと友人同士の親愛のキスを、ね」
チラと見ると、ルリアは先ほどから固まったまま動かない。
【ステイリー】
「友人同士…?親愛の、キス…?」
何を言ってるんだ、こいつは。
友人、というのは少し置いておいて、とりあえずどうしてこの状況になったのかだけは合点がいった。
「…ルリアさんに変なことを吹き込まないでくれないか」
他の世界ではそういうのもあるらしいがここではそういう習慣は、ない。
例え冗談でも外から来たルリアにそんな話をすればきっと真に受けてしまうだろう。
…璃王の場合単なる冗談ではないだろうけれど。
【ルリア】
サーっと血の気の引く音がした気がした
…キスの衝撃で吹っ飛んでたせいで完璧不意打ちをくらった気分だ
怒っただろうか?呆れてるだろうか?
告白したばかりの相手がいくらここでは普通の習慣とはいえ異性にキスしようとしてたなんて…
普通なら誤解する。
ようやく時間が動いたルリアは慌ててステイリーに縋り付いた
押し倒しかねない勢いで
「違っ…!そうですがそうじゃなくて…!!!」
頭の中はひたすらパニック状態
どうしたらいい?どうしたら伝わる?必死で考える
頭はパニックのまま、閃いた
友達に気持ちを伝える行為、それは今聞いたじゃないか
「私が…一番好きなのは…大好きで特別なのはステイリーさんだけです…!!!」
そのまま勢いで頬にキスをした
そして目を合わせて向かい合う
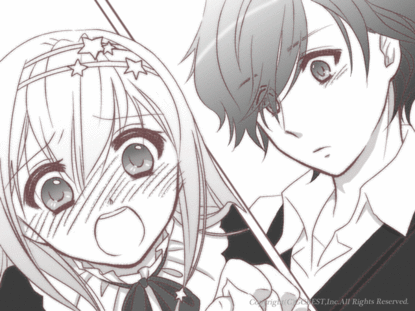
「私…本当に好き…です…!ちゃんと…!!
璃王さんとは友達になっただけです…!
今のは友愛ですけど…でも…でも……!本当に望むのは貴方だけです…!」
ルリアはひたすらパニックになると気持ちをそのままぶつけてしまう
一気にまくしたて、ステイリーに縋り、半分泣きそうな顔で彼を見つめる
【ステイリー】
――――――いま、何が起こった?
酷く慌てた様子のルリアに落ち着きを促す間もなく顔が近づいて頬に、触れた。
一瞬の出来事だったが驚きのあまり、またしても言葉が何も出てこない。
思考も体も固まっているというのに、心臓だけがいやに煩く脈打っていた。
【ルリア】
パニック状態のまま真っ赤になって行くステイリーを見る事数秒
堪えきれないかのように笑いを吹き出した璃王の声でルリアは我に帰った
………今…………自分は何をした?何を言った……?
自分の仕出かした事に改めて頭が付いてきて、そしてパニックが再来した
とっさにステイリーから離れた
「す…すみませ…!!
い、い、い、今のは本当に友好のキスですから…!!ここでは普通みたいなので…気にしないで下さい…!!!」
心臓は壊れそうな程脈打って、頭はパニックで
限界だった
「私…私……失礼しますー!!!!」
いつも通り、ルリアは脱兎して医務室から逃げ出したのであった
【璃王】
何か言う間もなく駆け去ってしまったルリアを見送る。
残されたのは固まったステイリーと自分だった。
結果は上々。
ほっと息をつき満足げに笑った。
(ルリアの誤解は…、後で解いておこう)
その時の反応を想像してまた笑いを漏らした。
あの少女が誰彼かまわず、などとは考え難いが、誤解したままではステイリーの心臓がもたないだろう。
ステイリーに向き直る。
「改めて…、目覚めの気分はどう?」
固まったまま動かない友人に二度目の問いを投げかけた。
【ステイリー】
璃王の言葉で我に返る。
寝起きだった頭はあまりの衝撃にもうすっかり目覚め、どうしてこうなったのかと思考を巡らす最中、ルリアの言葉が同時に再生され顔にさらに熱が上る。
「最高…、とでも言うと思うのか?」
実に複雑な気分だった。
ルリアの言葉が嬉しくないわけではないが璃王にしてやられた感がどうにも癪に障る。
どう考えても目の前にいる男が頬とはいえキスを仕向けたのは明らかだ。
「何か弁明があれば聴いてやらないこともないが…?」
平静を装うがいつものように笑う余裕はなかった。
【璃王】
「嫌だな。弁明も何も――
ボクはただ友人の幸せを願っただけだよ」
さらりと軽い口調で答える。
冗談とも取れる笑みを浮かべて。
(”多少”強引だったかもしれないけどね)
いつもの調子を取り戻せないステイリーを見て心の中でそう呟いた。
【ステイリー】
「余計な……」
璃王なりの気遣い、とでも言うべきなのだろうか。
まさしく自分にとっては余計なことではあったが途中でいうのを止めた。
どういう経緯かはわからないがルリアが言うのだ、璃王が言う友人という言葉の中には彼女も含まれているのだろう。
まったく、というようにため息が一つ漏れる。
「…寝なおす」
布団を被りなおし、璃王に背を向けて再び横になった。
熱の引かない顔を隠すように。
【璃王】
言葉短く布団にもぐりこんでしまった友人に、思わず微かな笑いを零してしまう。
これ以上からかうのは流石に辞めておこう。
「じゃあ、ボクは行くから」
パタンと静かにドアを閉め、医務室を後にした。
自分に起こった変化はと言えば、新たに友人と呼べる存在が出来たということ。
くすぐったくもあるけれど、悪い気分ではなかった。
「好き好き同盟、か」
今後二人の輪の中に入ることを許されたかのような気がした。
ただ――
(後で、ステイリーの小言を聞かせられることは覚悟した方が良さそうだ)
想像して、さてどうやってかわそうか、などと考えを巡らす。
あの二人にもう心配など必要ない。
ただ若しまた夢見魔法が必要になったその時は――。
(またいつでも力を貸すよ)
友人たちの幸せな様子を思い浮かべる最中、一人の少女の姿が思い浮かんだ。
(そうだ、ラミィの顔を見に行こう)
二人に当てられたのか、無性に逢いたい。
ラウンジの騒動の最中、鏡に飛び込んだ所までは見た。
今は部屋にいるだろうか、それとも移動魔法科の学科棟か。
知らず足運びが速くなる。
このアールトルーナで、ボク達はどんな未来を掴み取るのだろう。
行く末は誰にも判らない。
未来は定まってなどいなくて。幾らでも変えられるのだから。
それぞれの想いを乗せて時間は移ろいゆくのだった。

Fin.
*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*